
結納とは|結納を行う前に知っておきたい基本まとめ
アプリで記事を保存・購読
結納とは?伝統ある結納ですが現在はどのように行われているのでしょうか?
結納の歴史や由来、正式・略式から現在の結納まで基本的な知識をご紹介します。結納を行う前に知っておきましょう。
- 目次
結納とは「両家が婚約の印として品物を贈りあう儀式」


結納は、日本の伝統的な婚約の儀式で
結婚を約束した男女が婚約の印として品物を贈りあうこと。
結婚が家と家との結び付きであった頃から続くもので、互いに縁起物や現金などを贈り合い、両家の縁を結ぶ意味があります。そのため結納は「交わす」と表現されます。
列席するのは新郎新婦本人+両親の6名
結納は、両家の代表として両親、そして本人が列席します。結納は本人だけで行うものではありません。
どうしても両親が出席できない場合には、叔父叔母、兄姉夫妻など名代となってくれる人を立て、両家から本人以外に2名ずつ、合計6名で結納を行います。兄弟姉妹を同席させたい場合には、結納後の食事会からということになります。しかし、両家が納得して行う形式であれば臨機応変に対応しても構わないところも多いようです。
結納の由来は「結の物(ゆいのもの)と「言納(いいいれ)」から
昔は両家が婚姻関係を結ぶ際に男性が酒肴を持って女性の家を訪れていました。その際の酒肴が両家を結ぶ「結の物(ゆいのもの)」と呼ばれ、また、結婚の申し入れを「言納(いいいれ)」と呼んでいました。
それらが時代とともに変化して、「結納(ゆいのう)」になったとされています。持参した酒肴が結納品となった名残として、現在も結納の品目にはコンブやスルメが入っています。
💡 結納の品物や形式は地域により異なる
結納の品物や形式には地域により特色が見られます。関東を中心に結納の多くは男性側、女性側が共に結納品を贈り合います。両親や親戚にどういった慣習やしきたりがあるのかを聞いて調べておきましょう。
結納のスタイルは2つ|正式結納と略式結納


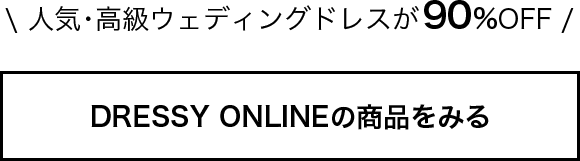



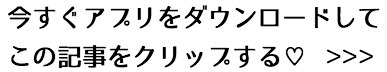
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)