
大人として心得ておきたいマナーの一つ、金封を包む「袱紗」。慶事と弔事で使い分けよう
アプリで記事を保存・購読
受付についてから金封を渡すまでの一連の所作の流れ

ここからは受付についてから、金封を渡すまでの一連の所作の流れを見ていきましょう。今回は結婚式に参列するイメージで、ご祝儀袋をお渡しするまでの流れです。
1.受付についたらお祝いの言葉を伝える
受付についたら、まずは係りの方にお祝いの言葉を伝えましょう。受付にいる方がもしかしたら知人や友人かもしれませんが、気軽なあいさつではなく「本日はおめでとうございます」と伝えます。
2.記帳を行う
ご祝儀を出す前に芳名帳に記帳を行うのが一般的です。記帳を行うことで受付の係りの方が出席者名簿の確認が行えます。
3.ご祝儀袋を袱紗ごと取り出す
バックから袱紗ごとご祝儀袋を取り出します。
4.袱紗からご祝儀袋を取り出し渡す
いよいよ袱紗からご祝儀袋を取り出します。右側に袱紗が開くように持ち、包みを開きます。金封袱紗の場合には、ご祝儀袋を取り出したら袱紗を閉じその上にご祝儀袋を載せます。風呂敷タイプなどの場合には、袱紗をたたんだ後に袱紗の上にご祝儀袋を載せましょう。このときご祝儀袋の表書きは自分に向いた状態で載せます。
袱紗ごとご祝儀袋を時計回しに回して、表書きを受付の方の方に向けましょう。ご祝儀袋をお渡しするときには、再度お祝いの言葉を添えるとよいですね。
5.袱紗をカバンにしまう
無事にご祝儀袋をお渡ししたら、袱紗をカバンにしまいます。金封袱紗や台付き袱紗はそのままカバンにしまってよいでしょう。風呂敷タイプや爪付きの場合は小さく折りたたんでしまうとコンパクトになりますよ。
弔事の場合は開き方や回し方が逆になる

今回は慶事の場合で詳しくご説明しましたが、弔事の場合は所作が逆になります。袱紗を開くときには左側に開くようにし、香典袋などを袱紗に載せた後は逆時計回りで受付の方に表書きを向けます。
最後にお悔やみの言葉を伝えることを忘れないようにしましょう。
大人のたしなみとして袱紗は最低でも一枚は用意しておくとよいでしょう

袱紗は大人のたしなみとして一枚は用意しておくとよいアイテムです。無地で濃い紫の袱紗であれば、冠婚葬祭のどのような場面でも使えるため便利でしょう。最近ではリバーシブルタイプのものもあるので、一枚だけ用意しておく場合には、リバーシブルタイプでもよいですね。
女性の場合は、慶事では華やかな装いに合わせ可愛らしいものを持っておくのもおすすめです。慶事用と弔事用のふくさがセットになって市販されているケースもあるため、ワンセット持っていてもよいですね。この先色々なシーンで使うことになるため、持っていて損はないアイテムといえますよ。
普段はあまり使わないものではありますが、いざというときにスマートに使えるよう、結婚式へ招待されたら一度練習をしておくとよいでしょう。ワンランク上の大人に見られるよう、袱紗を使う時のマナーを身に着けておきたいですね。
▽ご祝儀袋に関するマナーはこちら

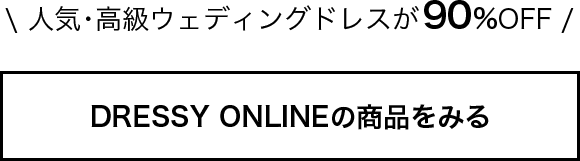



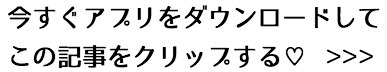
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)