
披露宴でスピーチを頼まれたら?エピソードの選び方やマナー、当日の流れについて
アプリで記事を保存・購読
披露宴には欠かせない、ゲストスピーチ。一般的には「主賓祝辞」と呼ばれる乾杯前のスピーチと、披露宴の後半に行われるスピーチとの2つがあり、主賓祝辞は新郎新婦の上司や恩師が、披露宴後半のスピーチは新郎新婦それぞれの友人代表が1人ずつあるいは多くて2人ずつ行います。
いずれにしても披露宴の雰囲気を大きく左右する大役。自分を信頼して頼んでくれた新郎新婦のためにも、素敵なスピーチをしてあげたいものです。
本番までの準備

通常、結婚式のスピーチは招待状を送るより前に新郎新婦から直接依頼されます。従って、本番(結婚式)の約2~3ヶ月間にお願いされるのが一般的。原稿作成期間や練習する時間、新郎新婦への確認などを考慮に入れると、意外に時間的余裕はないと考えておきましょう。
(1)原稿を作成する
スピーチを頼まれたなら、当然ですがまずは原稿を作ることから始めます。コツや注意点などは後述しますが、大まかな文章構成を説明しますと、まずは「御結婚おめでとうございます」の祝辞から始め、新郎あるいは新婦とどのような関係なのかを簡単にまとめた自己紹介をします。
続いてその延長上で新郎あるいは新婦の人柄が表れているようなエピソードを少し紹介します。最後に「お幸せに」等2人へのメッセージと「本日は誠におめでとうございます」「ありがとうございました」などの言葉で締めくくります。

(2)時間を調整する
これは原稿作成時にある程度意識しておくべきことですが、スピーチの長さは基本的に1人あたり3~5分です。媒酌人であればもう少し長くて5~10分、友人や同僚であれば逆に2~3分ほどが基本となりますが、いずれにせよ、どんなに良い内容であっても所要時間を超過して話し続けるのはマナー違反ですし、新郎新婦もゲストも聞き疲れてしまうでしょう。
それで原稿を作成し終わったなら、まずは所要時間内かどうかを確かめましょう。ストップウォッチなどを用意し、原稿を声に出して読んでみます。所要時間を超えるようならどこを削れるか考えましょう。よく見てみれば同じ言葉を繰り返しているところや、自分としては思い出深い内容でも、ゲストにしてみればそれほどではない部分などをカットできるかもしれません。
逆に短すぎる場合には、エピソード部分をもう少し膨らませると良いでしょう。

(3)確認を取る
場合によっては、スピーチの内容について新郎新婦に確認を取る必要があるかもしれません。例えばおめでた婚のカップルの場合、妊娠は伏せておきたいと考えているかもしれず、そうであればスピーチで赤ちゃんのことは触れてほしくないと思っているはずです。
勿論、当日の楽しみにとっておいてもらいたいのでスピーチの全てを伝える必要はありませんが、「もしかして話さないでほしいと思うかな」と感じるような部分については確認をとっておいた方が良いでしょう。
また文章に自信のない人は、友人や家族など第三者に原稿を見せたり聞いてもらったりして、チェックしてもらうと良いかもしれません。自分では正しいと思い込んでいた言い回しや言葉遣い、熟語や慣用句が実は間違っていたということもあり得るからです。
新郎や新婦を知っている人、知らない人の両方に聞いてもらい、内容がよく分かるかどうかも確認してもらいましょう。
(4)練習する
時間的にも内容的にも問題なし!と確認できた原稿は、当日までに何度も繰り返し声に出して練習しましょう。大抵の人は本番になると緊張のあまりいつも通りに話せないもの。落ち着いて話せるかどうかは練習次第です。
当日の様子をしっかりイメージしながら練習すれば、本番でも練習時と同じ調子で話すことができるようになるでしょう。
▽スピーチで知っておきたいマナーはこちら
コツや注意点は?


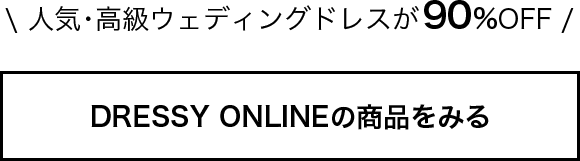



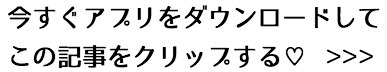
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)