
神社での結婚式もこれで完璧◎神前式の流れをまとめました
アプリで記事を保存・購読
- 目次
家と家の結びつきを大切にする神前式。日本伝統の式だけど、チャペル式と似ている式次第や見たことのあるシーンもちらほら☆知れば思ったより馴染みやすそう!主な式の流れと、それぞれにどんな意味が込められているのか知っておきましょう♡

①参進(さんしん)
巫女の先導を受けて、新郎新婦が神殿へ入場。赤い和傘の下を紋付羽織袴姿の新郎・白無垢姿の新婦が歩く姿は芸能人の挙式でも印象に残っているシーンとして人気です♪両家両親・親戚も一緒に入場したり、先に神殿で着座して待っていたりと会場によって入場方法が異なるので、ひとつひとつ、しっかり確認していこう☆オプションで雅楽の生演奏を付けるケースも。
②斎主入場(さいしゅにゅうじょう)
列席者全員が神殿に揃ったところで、式を執り行う斎主が入場。場内が厳粛な雰囲気に包まれる中、巫女や進行係の典儀が会式を告げます。
③修祓の儀(しゅばつのぎ)
一言で言うと、お祓いの儀式。斎主が大麻(おおぬさ)を振るシーンは初詣や七五三などで見たことがあるという人も多いはず。開式にあたり、新郎新婦をはじめ、列席者の穢れ(けがれ)を祓い、身を清めます。

④斎主祝詞奏上(さいしゅのりとそうじょう)
ふたりの結婚を斎主が神に報告します。式中では、新郎新婦は起立のまま、親族は儀式により起立・着席をしたりするところが多いので、体調などで気になることがある場合は事前にしっかりその旨を伝えて相談しよう。
⑤三献の儀(さんこんのぎ)
「三三九度」として知っている人のほうが多いかもしれませんね。大中小の三枚の盃に神酒が注がれ、それぞれを新郎、新婦の順に飲みます。一度目二度目は盃を傾けて口を付けるだけ、三度目で飲み干していきます。神に対し夫婦として誓いの盃を交わす最も厳粛な儀式です。

まだまだ続く!


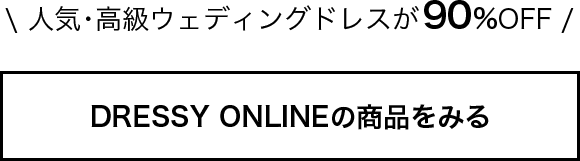



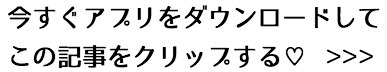
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)