
6月結婚すると幸せになれる?!ジューンブライドのメリットとデメリット
アプリで記事を保存・購読
6月に結婚すると幸せになれると言い伝えられる「ジューンブライド」。なぜ、6月に結婚すると幸せになれるのでしょうか?
その理由には諸説ありますが、大きく分けると次の3つが挙げられます。
- 目次
なぜジューンブライドは幸せになれるの?

まず最も有名なのが、ローマ神話の女神であるJUNOから生まれたとする説です。
JUNOは6月(JUNE)を象徴する女神で、結婚や出産など家庭生活を営む女性の守り神として、古くから信仰されてきました。JUNOが6月の神様であることから、この月に結婚した女性は幸せな結婚生活を営むことができると伝えられているのです。
2つ目の理由として、結婚式に最も適した気候の月だからという説もあります。ヨーロッパでは6月は爽やかで好天が続くため、結婚式に最適なシーズンなのです。
このため、気候の良い6月に結婚式を挙げるカップルが多かったといいます。ウェディングドレスを着ても汚れず、誰もが参加しやすいので、6月の結婚が好まれたのでしょう。
そして3つ目が、6月になるまで結婚が禁止されていたという説です。ヨーロッパでは種蒔きなど農作業で忙しくなる3月から5月は、結婚することが禁じられていました。
そして農作業が一段落する6月から、結婚式が解禁になるという習慣があったそうです。

同様に、作物の収穫期である秋に女性が出産すると、その時期は農作業に関わることができません。
このため、6月以降に結婚することで、収穫期と出産時期が重ならないよう調整する意味もあって、6月から結婚が解禁になったといわれています。
恋人たちは結婚が解禁となる6月になると、待ちかねたように結婚式を挙げました。6月は結婚式のムーブメントが巻き起こり、街がお祝いムード一色となることから、ジューンブライドという言葉が生まれたとされているのです。
日本でもジューンブライドは意味があるの?

ヨーロッパでは6月は、結婚式に絶好のシーズンとなります。しかし日本では6月は梅雨の時期に当たり、結婚式に向いているとはいえません。ヨーロッパで生まれたジューンブライドは、日本でも意味があるのでしょうか?
ジューンブライドが日本でも知られるようになったのは、結婚式業界の宣伝活動がきっかけです。日本の6月は、ジメジメ・ジトジトした梅雨のシーズンです。一年のうちでも、結婚式を挙げるカップルの数が激減するため、ホテルなどブライダル業界の売り上げが落ち込みます。
これに困ったホテルオークラが、1967年頃からPR戦略として採用したのが「ジューンブライド」でした。6月に結婚すると幸せになるとアピールすることで、6月期の売上高を少しでも上げようと考えたのだそうです。このPR戦略が功を奏し、日本でもジューンブライドという言葉が浸透するようになりました。
ジューンブライドが単なるヨーロッパの言い伝えなのか、本当に幸せになれるのか、気になる方もいることでしょう。
厚生労働省が発表した「平成21年度 離婚に関する統計」によると、平成20年における月別の離婚件数で、最も多かったのは3月の10.3%でした。次いで4月の8.9%、10月の8.6%、12月の8.5%……と続き、6月の離婚率は7番目の8.1%となっています。
この数字だけで、ジューンブライドの信憑性を検証するのは難しいのですが、困難なことにぶつかっても「ジューンブライド」だから、夫婦で乗り換えていこう!など、6月に結婚したことが心の支えになって、困難を乗り越えるパワーが得られると考える人は多いのです。ヨーロッパ由来の言い伝えであっても、ジューンブライドは縁起が良いことに変わりはありません。

洋の東西を問わず、誰しも幸せな結婚生活を送りたいものです。日本には、「雨降って地固まる」という言葉もあります。
ハレの儀式では特に縁起を担ぐことを大切にしてきた日本人にとっても、ジューンブライドは幸せを呼んでくれる素敵な言い伝えといえるでしょう。
しかし、いくら幸せになれるといっても梅雨の時期の挙式は、お天気が大きな不安要素となります。ジューンブライドに憧れるけれど雨が心配……という方は、次のような対処法を取ってみるにも一案です。
▽ジューンブライド成功の関連記事はこちら
雨対策を見る!


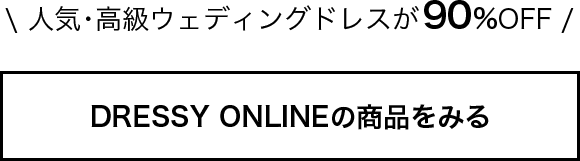



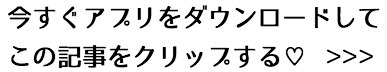
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)