
入籍=結婚ではない?入籍と結婚の正しい意味とは
アプリで記事を保存・購読
本来の入籍の意味とは?「私たちは〇月〇日に入籍いたしましたことを、ここにご報告いたします。」といった有名人・芸能人の結婚の報告の文章の中で、入籍という言葉を耳にすることがあります。この場合、「入籍」という言葉を「結婚」という意味で使っていることになりますが、本来は、結婚=入籍ではないことをご存知ですか。
それなのになぜ、結婚=入籍という使い方をしてしまう人が少なからずいるのでしょうか。ここでは結婚=入籍ではないことの説明と、「入籍とはそもそも何か?」という疑問にお答えします。
じつは入籍=結婚ではない

戸籍法上の入籍とは、すでにある戸籍に新たに加わり、その戸籍の一員となることを指します。婚姻届を提出することにより、一般的には、親が筆頭者となっている戸籍から出て、新たに夫妻の戸籍が作られます。従って入籍とはなりません。
入籍とは籍を入れること、戸籍に入ることであり、出生や養子縁組などによって籍を入れることも含まれます。なかには、入籍=結婚となるケースもあります。すでに戸籍筆頭者となっている夫または妻の配偶者となり、その姓を名乗る場合には、入籍=結婚となります。
このように、その多くが入籍=結婚とはならない中で、なぜ入籍をいう言葉を結婚という意味で使っている人が多くいるのでしょうか。それは明治時代の旧民法における婚姻に起因します。当時は婚姻により夫や妻の家へ嫁入り、婿入りして、相手方の戸籍に入っていたことから入籍=結婚でした。そのため、新しい民法となって入籍=結婚ではなくなった現在も、慣習として入籍が結婚と同義であるように使われ続けているのです。
そのため、「入籍しました」と伝えることで、多くの人に「結婚した」ということは伝わっているのですが、入籍=結婚ではないことを知っている人からは、間違って使っていることを指摘されることがあるかもしれません。法律が改正されてからの期間を考えると、正しい言葉を使えるほうが好ましいと言えそうです。
入籍とは戸籍に入ること
入籍とは、籍に入ること、戸籍に入ることを言います。
市区町村役場には「入籍届」という申請書類があります。これは、現在の戸籍から出て、別の戸籍に入るときに使う申請書類です。「入籍届」を使う場合としては、認知した子どもを父親の戸籍に入れる場合や、再婚する人が前の配偶者の間に生まれた子どもを再婚先の戸籍に入れる場合、離婚するときに子どもを引き取り自分の戸籍に入れる場合などがあります。従って、結婚をする際の申請書類とは異なります。
結婚をする際はどのようなケースであっても基本は「婚姻届」を提出することになります。なお、入籍と反対の意味を持つ言葉は「除籍」であり、離婚ではありません。離婚により戸籍の筆頭者以外の人はその戸籍から除かれますが、除籍には離婚や死亡などが含まれるため、入籍=婚姻ではないように、除籍=離婚ではありません。
結婚とは妻と夫になること。


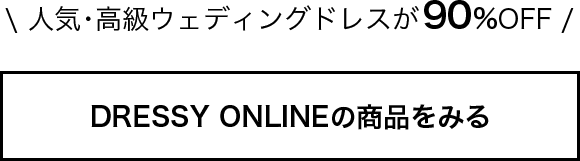



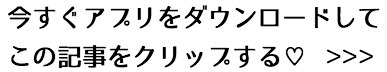
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)