
嫁入り道具とは何?持っていくべきアイテムと不要なアイテム
アプリで記事を保存・購読
嫁入り道具として用意されていたもの

嫁入り道具として、昔は桐のたんすにたくさんの着物を詰めて新しい家に嫁ぐ風習がありました。現代ではそもそも着物を着る習慣自体がなくなってきていますので、桐たんすも着物も用意する方は少ないです。昔は着物を日常的に着ていた上、訪問先やシーンに合わせて、ランクの違う着物を着こなす必要がありました。
訪問着や小紋、留袖など様々な種類の着物を用意しておく必要があり、着物を嫁入り道具とする習慣があったのです。
現代で言うドレッサー、昔は鏡台と呼んでいましたが、こちらも代表的な嫁入り道具です。昔は「三面鏡」と呼ばれるタイプの鏡台を用意する家庭が多く、大きな存在感を放っていました。しかし、現代ではそもそもドレッサーを持っている方も欲しがる方も少なくなってきているので、わざわざ用意する必要がないとされています。

婚礼布団も、嫁入り道具として代表的なものだと言えます。普通の布団よりもボリュームや厚みがあるので、高級感があります。見栄えの良い布団を持たせることで家柄の良さを披露する目的があり、中には近所の人を集めて披露する会が開かれていた地域もありました。婚礼布団は新郎新婦のものをはじめ、お客様用のものも用意する家庭もあり、布団だけで10万円以上の価値があったケースも散見されます。
特に、布団にこだわる地域や羽毛や綿などが特産の地域では、布団にかける費用や選ぶ時間も多大なものでした。現代では布団で寝ている方も少ないですし、そもそも布団をしまう押入れがある家も少なくなってきているので、婚礼布団の習慣はかなり少なくなってきています。
このように、嫁入り道具として、たんす、着物、鏡台、布団などが用意されていましたが、現代では「必要ない」と判断されるものが多く見られます。
なぜ嫁入り道具の風習がなくなったのか?

昔の嫁入り道具はとても重視されている風習でしたが、現代では嫁入り道具や結納はなしとするパターンも多くなりました。それには様々な要素が絡んでいますが、「結婚」に重きをおかなくなった現代の考え方が大きく関係しているとされています。
また、核家族化が増えてきており、家同士の結婚というよりは、本人同士の結婚という認識が強まってきたことも大きく影響しています。わざわざ結納や嫁入り道具を持たせること自体、家同士が「面倒」と考えることも多いので、結婚する際にはできるだけ簡素化しようと考えている家庭も少なくありません。
また、嫁入り道具を持っていっても実際には使わなかったり、邪魔になったりするケースも少なくないため、「無駄な費用は削減しよう」と考えている方も少なくないでしょう。特に現在、景気が良いわけではありませんので、嫁入り道具を持たせること自体に意味を感じる人が少なくなってきているのです。
▽新生活に関する記事はこちら
現代ではどんなアイテムが必要?


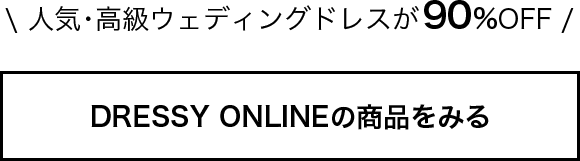



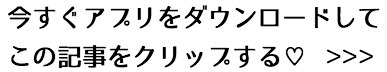
![【高級ウェディングドレスが最大90%OFF】DRESSY ONLINE[ドレシーオンライン]は、ウェディングドレスメディア「DRESSY[ドレシー]」の公式ECサイト。](https://www.farny.jp/wp-content/themes/kg-farny/img/article/wedding_dressyonline.png)